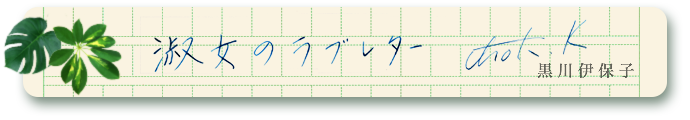
この春、父が逝った。
85歳の誕生日の朝、「腸が食べ物を吸収しない。もういい」と言ったきり、飲食を止めてしまった。
十分に時を重ねた脳は、〝逝き方”を知っている。水分やブドウ糖が供給されなくなると、脳内麻薬と呼ばれるホルモンが分泌されて、恐怖心や痛みから解放される。脳は、その最期のとき、とても気持ちよく逝くのに違いない。脳科学上は、そうとしか思えない。
その理論を証明するかのように、父は穏やかにうとうととまどろんだ後、三日目にこの世を離れた。脳の研究を生業とする娘に、逝き方の見本を見せてくれたような、そんな最期だった。
父は、栃木の小さな町で、高校の社会科の教師として生きた。
亡くなる3週間前には、大学生の孫息子とフランス革命について語り合っている。父の卒論のテーマだったそうだ。
その最後に、父は孫息子にこう声をかけた。「お前は、世界史をやったかい?」。
「ああ、やったよ。受験科目だった」
と答えた孫息子に、父は微笑みかけた。
「世界史は、残念ながら、不完全な教科なんだよ」
世界史を40年近く教え続けた父は、そんなふうにつぶやいた。
戦後、この国の若い人たちに、世界を公平に俯瞰できるようにと用意された学科なのだが、世界には「公平な俯瞰」などないのだと、父は言う。
たとえば、十字軍遠征は、ヨーロッパ側から見たものと、イスラム側から見たものは、まるで違うものだ。それを俯瞰して書くことは、たやすいことじゃない。
結局、この科目は、西洋史と東洋史を切り貼りしてつなげただけで見切り発車した。そのまま、成熟を見ないまま、世界史という教科は今に至っている。
父は、ただ淡々と、自分が付き合ってきた教科をそう評した。悲しむわけでもなく、憤るわけでもなく。
私は高校時代、父の教え子として世界史を学んだのだが、父は教科書を超えて「公平な俯瞰」になるだけ近づこうと努力していた。その板書のいくつかを今でも思い出せる。
父の板書は、ノート見開き2ページにそのまま移せば、その日のテーマとなった歴史イベントが多角的に見えるように、緻密に設計されていた。父が自身のノートにその板書デザインを作りあげるため、何年もかけていたのだ。
あのノートをもう一度見たい。
父が亡くなった後、父の書棚をひっくり返してみたのだが、残念ながら、父と〝世界史という教科〟との戦いの記録を見つけ出すことはできなかった。
その代り、日本国憲法の英語草案の書を見つけた。
ああ、そうか……!と、私は胸を打たれた。退職後、父は英語の勉強に夢中だった。単なる年寄りの暇つぶしだと思っていたのだったが、父は、彼自身の原点に戻ったのだった。
父は、17歳で終戦を迎えた。理系だった父が、戦後、東京教育大学の政治学科に進んだのは「この国の背骨を立てるためには、政治を知らなきゃいかん」と思ったからだそうだ。その父は、生涯にわたって、日本国憲法のひずみを案じていた。晩年、父は英語をマスターして、GHQ草案をちゃんと読もうと決心したのに違いない。
世界を公平に俯瞰しようとしたその傍らで、日本国憲法の歪みを案じる。政治家や文化人のように声を高らかにしなくても、市井で国を憂える父のような男たちは、この国にたくさんいるに違いない。
今年の春まで、父の同級生たちが、毎年同窓会を開いていた。東京教育大学で昭和20年代に法律政治学を学んだ男たちである。
父は、69歳で脳梗塞を患い、ボケはしなかったが、まっすぐ歩くことが出来なくなってしまった。そのため、晩年の同窓会には、私が同行した。
この同窓会、必ず、憲法論・天皇論・君が代論で荒れるのである。
皆、戦後の教育現場を支えたエリートたちだ。日教組を創ったといっても過言ではない大半の同級生に対し、父は、「戦後、日本は、へたれて、戦わずして〝世界〟に負けてしまった。その戦犯は、日教組と朝日新聞だ」と明言する愛国主義者だ。当然、絶対に相容れない議論が湧き起こる。
でも大丈夫。会場がそうとう険悪になったところで、誰かが上質のジョークで、場を和ませる。全員が上手にそのジョークに乗って、後は校歌や寮歌で盛り上がるのだ。彼らは、この〝興行〟を大学時代から何十年も繰り返しているのである。
男たちは、本当に、憲法論が好きだ。憲法論に限らず、論を語るのが好き、戦わせるのが好き。そして、実際にぶつかれば激高するくせに、論敵に値するだけの友を心から愛する。
これらの癖は、女性たちにはない。女子大の同窓会でも、女性経営者の会でも、論敵に匹敵するだけの教養と経験のある女性たちが集まるのだが、誰も論をぶとうとはしない。私たちは、体験を語り合い、そこから得た普遍の何かを共にしみじみ味わうだけだ。
女は共感するために会話をするからね。最適解を得るために、選択肢を並べて協議したがる男の会話とは、目的が違う。
だから、憲法論を、女は好まない。「共感して、しみじみ味わう」ポイントがないからだ。歴史の事件ならまだ共感のしようがあるが、「枠組み」の定義なんて、とんと女心をくすぐらない。
女性の会話が共感を基本とするのは、女性の脳が、共感によって知識を増やすからだ。
女性脳の中では、体験記憶に、そのときの情動(心の動き)が見出しになって、しまいこまれている。このため、同様の情動が起こったときに、過去の関連記憶が一気に脳裏に展開されるのである。
たとえば、子どもが熱を出した晩。いつもと熱の出方が違って不安に陥ったそのとき、何か月も前に公園で立ち話したママ友達のことばや、幼い日に母がしてくれたことを思い出す。
女性脳は、人生の経験のすべてを瞬時に使って、現状に対応する。それは、総括的な知識体系から繰り出される絶対的な正解ではないが、けっこう使える〝見繕い解〟。あらゆるシーンに対応できる臨機応変な力だ。
数少ない個体を生み出し、命がけの子育てを担当する「哺乳類のメス」である女性に与えられた才能である。
一方の男性脳は、狩りに出て、獲物と遭遇したら命がけで闘い、ちゃんと棲み処に帰ってこなければならない「哺乳類のオス」の脳である。
男性脳の真骨頂は、瞬時に、最適解を選び出すこと。つまり、結論を急ぐ。
広い空間を把握して道に迷わず、遠くから急接近してくるイレギュラーな物体(敵にしろ獲物にしろ)に脳の照準を瞬時に合わせるためには、他人の体験談に心を寄せて、動揺したり、気を散らせたりするわけにはいかないのである。
そもそも男性脳は女性脳よりも、脳梁が細い。脳梁は、右脳と左脳のニューロンを連携させている神経線維の束である。男性脳は右脳と左脳の連携が女性よりも弱いのだ。左脳の論理領域で、論理演算をするときに、右脳の直感の領域に頻繁に繋がらない。つまり、ときには自分の体感や感情からさえも論理演算を乖離させることが出来るのだ。生活感と思考の乖離である。
だから、「歪んだ重力場」や「ループする時間」などを論じる宇宙物理学の世界は、圧倒的に男性比率が高い。目に見えないもの、観念的なものについて抽象的に思考することが得意である。
勿論、そこにはデメリットもある。何かに熱中してしまうと、自分の生活を省みることを忘れる。だから帰りの電車賃までギャンブルに突っ込むのは、男性ばかりだ。
男性脳に体感・生活感と乖離したジャッジができるからこそ、天才も生まれるし、「社会に何かを訴えるため」の概念による連続殺人も起こしたりするのである。
さて、イレギュラーな存在に瞬時に照準を合わせるためには、「定番の世界観」をしっかり不動にしておかなくてはならない。
だから、男たちは定番にこだわる。行きつけの床屋や店を簡単には変えないし、ものごとの序列がついていて、容易にはその序列が変わらないことを望む。
無邪気に遵守する枠組みや序列の「定義」を、だから、とても大事にする。憲法は、国の枠組みだ。だから、男たちは、黙ってはいられない。
女にしてみれば、決め事や序列は建前に過ぎない。解釈の幅が格段に広くて、ときどきに都合のいい答えを見繕える女性脳は、「ルールはわかったわ。で? それで、今回はどうするの?」なんて聞いてくる。
だから女たちは、男性脳が作り上げた憲法そのものにも、それについて論議することにも、どうしても遠巻きになってしまうのだ。
話は、父の同窓会に戻る。
父が最後に同窓会に参加したのは、70代の終わりごろだったと思う。
このとき、天皇制廃止論のおじさまが、「吉沢くん(父の名である)、きみに謝らなければならない。僕は長らく天皇制廃止を訴えてきたが、前言撤回だ」と言うではないか。
この方が出場したシニアの水泳大会に、皇太子ご夫妻がお見えになったのだそうだ。いわく、お声をかけられたら、あまりにも嬉しく、誇らしい気分になった。あの気持ちがどこから湧き上がったのか、自分でもわからない。あれは、理屈じゃないね。この国に、あるべき存在なのだ。
私は、くすりと笑ってしまった。天皇家が理屈じゃないことくらい、女たちはみんな肌で知っている。あのお家は、祈りの中枢なのだもの。
男たちときたら、なんて不器用で、可愛らしくて、そして崇高なのだろう。
政治家が論じる憲法の方は、なかなか決着を見ない。それでも、市井に憲法論を戦わす男たちがいる限り、私は、この国を信じる。
(新潮45 2013年8月号 掲載)