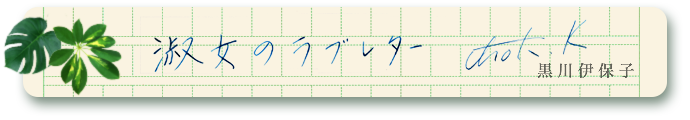
秘蔵の書~『字通』(白川静著、1996年 平凡出版)
私は、ことばのフェティシズムなのだと思う。
江戸情緒の残る、東京下町、根津辺り。大きな商家の離れのような、粋なしもた家の前を通ると、こんな家に住んで、愛しいひとに三つ指をついて、「今宵、あなたのお好きな名で呼んで、可愛がってください」なんて言って暮らしてみたい、などと妄想してしまう。
今時なら、ほおずき、つゆくさ、やなぎ、てっせん。意外に、しょうがも可愛い。すいか、なんていう晩があったっていい。密やかな気持ちの晩には、ほたる、かしら。やがて、すずむし、くちは(朽葉)、ひいらぎ。
季節の折々に、季節の句読点になるような名で呼ばれ、季節の化身になって、惚れた男に寄り添いたい。
都会の片隅なのがいいのである。実際に、はかなげな青白い光の飛来する水辺で、生身の中年女を「ほたる」とは呼びにくいだろう。本物から遮断されていればこそ、出来の良くない化身も許せるはず、という健気な作戦である。
仕事も子育ても、介護も家事も、みんな忘れて、ほたる、と呼ばれて透明になる宵が、そろそろあってもいいのじゃかいか、と思うのだが、現実は厳しい。小学六年の息子は育ち盛りで、私の顔を見れば、第一声は必ず「腹、減った」である。今月発売の書き下ろしの本の最終校正も、先ほど夕飯時にFAXが入ったばかりである。そこへ、PTAの連絡網の電話がかかってきて、なんだか長々と話が終わらず、一方、私の大好きなひとは仕事に追われて、連絡も取れない。「ほたる」時間は、この夏もやってきそうにないのである。
それでも、深夜、子どもが寝ている脇で腹ばいになり、植物図鑑や歳時記を開いて、季節のことばを拾うのが、ここ十年ほどの私のささやかな悦びだ。子どもの安らかな寝息と、まろやかなことばたち。後の人生で思い返しても、きっと人生至福のときなのだろう。もしかすると、実際の「ほたる」時間よりも、ずっと・・・
さて、そんな私に、さらなる悦びを与えてくれたのが、白川静先生の「字通」だった。
ことばを構成する以前の字、ひとつずつ。その一文字一文字の由来、来歴と機能構成を書き連ねた、まさに王道の字書である。文章そのものは精緻にして揺れがない。字書のための、専門家向けの文章だ。
なのに、読み進めてゆくと、どこか人間臭さが匂い立ち、なんでもない文字の歴史と存在感がときにしみじみと、ときにコミカルに伝わってくる。それは、字書というより、文字たちのものがたり、なのだ。
その情緒感は、どこから来るのだろう、と改めて考えてみれば、それは、一文字に対して与えられる圧倒的な情報量だろう。漢字のたった一文字を、これだけの情熱的な緻密さで見つめられる、白川静という人の常人を超えたちからを思わずにはいられない。
そして、何より、白川先生が、ことばを愛しているのだと思う。ことばの構成要素としての文字が、ことば全体に与える神秘の奥行き。たとえば、私の名、伊保子の伊は、「神官が神杖を持って立つ姿」とある。なんでもない名に、神秘のメッセージが加わる。私がほたると呼ばれて、ほたるの化身になってもいいよ(見た目はぜんぜん違うけど)と、自分自身の名と、白川先生に許してもらったように思うのは、私の穿ちすぎかしら?
(朝日新聞出版局「一冊の本」2003年7月号掲載)