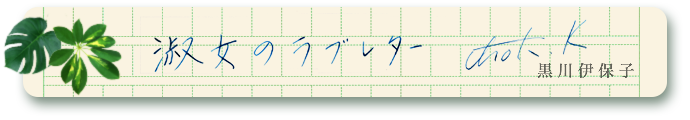
「あなたの声は、触感を刺激する。あなたは、触感の魔女だね」
初対面の私にそうおっしゃったのは、ルネ・ヴァン・ダール・ワタナベ氏である。日本の雑誌に今や欠かせなくなった星占いは、この方が雑誌「non-no」や「女性自身」に掲載したのが草分けと言われる。占星術師として有名になられたが、本来は神秘学の研究者であり、感性を研究している私にも、「人が感じること」の豊かさや意外性について、多くのヒントをくださった。
さて、冒頭のセリフは、初めて言葉を交わした直後のこと。ほんの2~3言交わしただけで、この方は、私の本質を見抜いたのである。私は、ことばの触感の研究者だ。
「はい。私はなによりも、ことばの触感を、聞き手に伝えたいと思ってしゃべっています。私にとって、ことばは触感ですから」
胸を突かれてしばらく絶句したのち、私はそう答えた。
私がもらった、生涯最速にして最も深い理解のことば。故ワタナベ氏は、どんな目で、世の中を見ていらしたのだろう。いや、触覚というべきか…?
ことばには、触感がある。
たとえば、S音を発音するとき。息は、口腔表面をあまねく撫でるように滑り出る。
上あごや舌には細かい凹凸がある。この上に息を滑らすと、「流体の移動距離に対して、触れる表面積が大きい」という熱力学的事象をつくり出す。これは、空冷装置と同じ構造で、息の温度を一気に下げるのだ。
S音は、だから、爽やかなのである。爽やか、涼やか、清涼感、爽快…これらはすべて S音はじまりのことばだが、それは偶然ではない。S音を意識して発音してみれば、どなたにも口腔内温度が下がるのがわかるはずだ。
ちなみに、口腔表面を擦ることばの音は、S音以外に、ツとヒがある。どちらも、「冷」の読み(つめたい、ひえる)に使われていて興味深い。ヒは、肺の中で温められた熱い息が喉の一点に当たるので、まずは熱い。そして、口腔表面を滑った息が冷たく唇に当たる。日本語の音の中で、最も熱く、最も冷たい音でもある。そして、日本人は、火にも氷(氷雨、氷室)にも、この音を当てている。
サ行音の中でも、サとセは、特に息が強く口腔表面を拭う。後腐れのない、穢れを拭い去った感覚が口元で起こっているのである。「さっぱり」「爽やか」「清潔」「清涼」は、その意味の出来事が、口腔内で再現されている。
さらに、発音後、潔く口を開けるサは、口腔表面が乾くので、「さばさば」したドライな印象も含んでいる。「さぁ、さっさと行こう」と言われれば、未練を残す暇もない。
口腔を低くして、舌を平たくするセには、広く遥かな感じが伴う。「生前」と表現したとたんに、故人は、穢れを拭われ、静かに遠くなる。
ソは、少し特別だ。S音を発した後、口を大きな閉空間にするので、口腔を滑る息が、優しくソフトなのだ。さらに、その一部が口腔内に循環してほんのり温められる。このため、クールダウン&ウォームという癒し感覚が伴うのがソの特徴でもある。
不満や怒りを溢れさせている人の話は、「そう」「そうなの」「それはひどいね」という相槌で聞く人が圧倒的に多いが、これは、無意識のうちにソの触感で、相手をなだめているのである。優しく撫でて、クールダウンして温めて、包み込む。たった一拍のことばの音に、それだけの「ものがたり」があり、それだけの力がある。
ことばには触感がある。口腔という感じやすい場所に息を擦らせ、声帯や舌を振動させて発音している以上、当たり前のことだが、意識している人は少ない。ことばの触感は、小脳が牛耳っており、ここは無意識の領域の器官だからだ。しかし、ここは、空間認識を司り、イメージ生成の基盤となる場所。発音触感のものがたりは、意外にも大きく、私たちの脳に影響しているのである。
私自身は、だから、語感の正体は、発音時の体感(ことばの触感)であると定義している。もちろん、耳の聴こえ(大脳聴覚野)の影響もあるのだけれど、小脳の処理は、大脳の処理に先んじて起こるし、聴覚と触覚が感じることは、そんなに違っていないからだ。たとえば、筋肉を硬くして出す音(K音やT音)は、耳で聴いても硬い感じがする。硬い金属を叩けば、硬そうな音がするのと同じように。
聴いた感じを客観的な指標にするのは難しいが、舌の硬さや息の強さ、上あごに当たる舌の密着面積などは客観的に語れるし、相対数値も与えることができる。ということはコンピュータで語感を数値化することもできるわけで、将来、ロボットにことばをしゃべらせるとき、「癒し語感モード」とか「爽やか語感モード」を設定することだって可能だ。語感研究を、ことばの触感に絞れば、科学の俎上に載せることができるのである。ちょっと未来的で、わくわくしませんか?
とはいえ、このことを最初に指摘したのは、かのソクラテスである。それは、2400年ほども前のこと。ソクラテスは、プラトンが残した「クラテュロス ~ことば(あるいは名前)の正しさについて」という文献の中で、「ことば(あるいは名前)とは、それが指し示すところの事象の、口腔による模倣である」と語り、その一致を見る言語体系こそが正しいと説いている。
爽やかな朝、優しい夜。
どちらもよく聞く組み合わせだと思う。前者は、晴れた日の朝のTV番組で、後者は歌謡曲の歌詞で。
けれど、形容詞と名詞の組み合わせを逆にすると、どうだろう。優しい朝、爽やかな夜。あまり聞いたこともないし、改めて聞いてもなんだかぴんと来ないのではないだろうか。
とはいえ、実際に「優しい朝」がないわけじゃない。信州生まれの私は、寒気が緩む春の朝を確かに皮膚感で「優しい」と感じたし、学生時代は奈良にいて、ミルク色の朝もやが立ち込める盆地の朝を視覚的に「優しい」とも感じていた。
「爽やかな夜」も同じだ。たとえば夏の高原の夜、清々しい風に吹かれて、きらめく星座を見上げる。それは、きっと爽やかな環境なのだけど、「爽やか」ということばはどうにも似合わない。
サワヤカの発音は、語頭のサと語尾のカが、口腔内に吹き渡る風と開放感をもたらしている。朝らしい朝の風景そのままだ。
中盤のワヤは、膨張と揺れの音。ワは、ウアを一拍で発音する。口腔に奥まった感じをもたらすウから、開放感をもたらすアへの一瞬の変化なので、膨らむ感じがするのである。続くヤは、イアを一拍で発音する。口腔に鋭い緊張感をもたらすイから、開放感をもたらすアへの一瞬の変化なので、舌が揺れるとともに緊張緩和をもたらす。
この組み合わせは「物事が膨らんで揺れ、やがて弛緩する感じ」を作りだす。まさに関西弁の「わや」に当たる。「爽やかな朝」におけるワヤは、「これから始まる一日のさまざまなこと」を彷彿とさせている。
だからだろう。サワヤカがもたらす開放感と雑多な躍動感は、朝にこそふさわしく、いかに清々しい空気の下であろうと、夜の帳(とばり)には似合わないのである。
私たちは、無意識ながら、そのことを知っている。そうして、自然に、ことばの組み合わせをチューニングしているのである。
こうして、ことばの触感は、潜在意識に深く入り込み、イメージを確立する。
人の名だと、その名の持ち主に対して、一定の期待を生み出すのである。シュンスケは、口腔内を3度風が吹き抜け(シュ、ス、ケ)、発音点が行ったり来たりする(シュは歯、ンは喉、スは歯、ケは喉)。機敏に動くスポーツ少年を彷彿とさせる。シュンスケが愚図だと、女の子は、かなりがっかりする。
いっぽう、息が口腔内に三回留まるマナブくんやマコトくんは、機敏に動くことは期待されていない。だから、スポーツ少年じゃなくても大丈夫だが、勉強か趣味(長く時間をかけてものにすること)に長けていないとがっかりされる。
あなたの名は、どんな期待をかけられているのだろうか。
口腔に起こる触感のものがたりを意識して、何度か発音してみてください。きっと、名に寄せられた「いのちへの期待」が降りてくるはずだ。
自分の個性と、名に込められた期待感がずれていたらどうしようと不安になるだろうか。でも、大丈夫。生まれたての赤ん坊が発するいのちの色合いは濃くて見逃しようがない。ほとんどの赤ん坊が、その個性にふさわしい名を得て、その名の通りに育っていくからだ。
この7月、桂三枝さんが「六代目 桂文枝」を襲名された。
爽やかに表面を滑るサンシに対し、舌に雑振動を作りだすブンシは、容赦なく中に入り込んでかき回す触感だ。サンシが爽やかな撫でるようなコミュニケーションを期待されるのに対し、ブンシは「人とのぎくしゃく」を楽しむことば。ちょっとした痛みを伴うくらいのけれん味と、他者の領域に一歩踏み込むことを期待される名なのである。今までの芸風に、きっと新たな展開を重ねなければならなくなる。しかも、この方の場合、正反対の色合いを持つので、深い玉虫色の輝きを見せてくださるに違いない。
ファンとしては願ってもないことだが、こう見ると、襲名とは厳しいものだと思わざるを得ない。
そういえば、ほぼ同時期に市川猿之助を襲名された亀次郎さんも、最初はかなり戸惑っていらしたようだった。カメジロウは、傍にいて離れない感じがする触感で、甘い余韻を残す。秘密の若い恋人のような、愛おしい語感なのである。対するエンノスケは、人との距離を遥かにとってしまう。口腔を低く広く使うエとケ、息を遠くへ飛ばすスの効果である。
亀次郎さんのファンにとっては甘えん坊の息子が巣立つようであり、亀次郎さんにとっては、「エンノスケさん」と呼ばれるたびに、周囲が遠く感じてしまうのではないだろうか。憧れを誘う素晴らしいスターネームだが、カメジロウからの変化では、かなり寂しい感じがするはず。しかしながら、それを乗り越えて、この方は大きく飛翔していかれるのだろう。
襲名の妙が創り出していく、芸の深みがある。逆に言えば、何人ものいのちを与えられて完成していく「超人格」が、この名の下にある。日本文化の中の、特筆すべき点だと私は思う。
最近、私は乳首をコレクションしている。
猟奇的なことではないので安心してください。哺乳瓶の吸い口の部分のことである。実は、世界各国、乳首のかたちがずいぶん違う(重ねて言うが、哺乳瓶のそれである)。
日本の乳首は、電球型。全方位に無邪気に丸い。これは、実際のママの乳首に近い形なので、世界中の赤ちゃんが、この形の哺乳瓶を与えられていると信じていたら、実はそうではないのである。
口腔を低くして、上あごを強く擦る子音を多用するドイツ語圏の赤ちゃんは、硬く平たい乳首を与えられている。いかにも、将来、「シュツッ」だの「シュケッ」だのを多用するタフな口元になりそうな乳首だ。
日本語とよく似た母音優位の発音をするイタリアは、日本と同様の電球型。母音アイウエオをしっかりと発音する両国は、ことばの発音において、口腔を上下に微細にコントロールする。「アルデンテ(パスタの絶妙の湯で具合)がわかるのは、日本人とイタリア人だけだ」とイタリア男はよく言うが、これは単なる口説き文句というわけじゃない。本当に、この二つのことばの使い手は、食べ物の弾性に敏感なのである。
エジプトの乳首には、内側に、ななめの筋が付けられている。つまり、口に含んで吸うと、乳首が少しねじれて、ミルクが運ばれるのだ。絞り出す、という態になる。アラブ語は、たとえば、コーランを唱える音声を聞いていると、深く響いて揺れる独特の子音を持っている。日本人の私にはわからない方法で口腔を使うのだろうとは予想していたが、あのねじれの乳首に、その子音を育てる秘密があるのかもしれない。
赤ちゃんは、話しかけられると、その表情筋をそのまま脳裏に映しとる。授乳中話しかけられたことばの触感を、そのまま舌でなぞらえているので、ドイツ語で話しかけられる赤ちゃんは、ドイツ語の発音構造に似合った乳首が気持ちいいし、当然、各国そうなのである。
けれど最近、授乳中に携帯端末に夢中で、ろくに話しかけないお母さんが増えていると聞く。その赤ちゃん、何語に長けた口腔に育つのだろうか。
ことばの触感で世の中を見ると、意外なことが見えてくる。私自身のことばを遊ぶ旅(経理処理上「研究」と呼んでいるが)は30年を超えたが、まだまだ終わりが見えない。
(集英社「Kotoba」 2012年秋号 掲載)